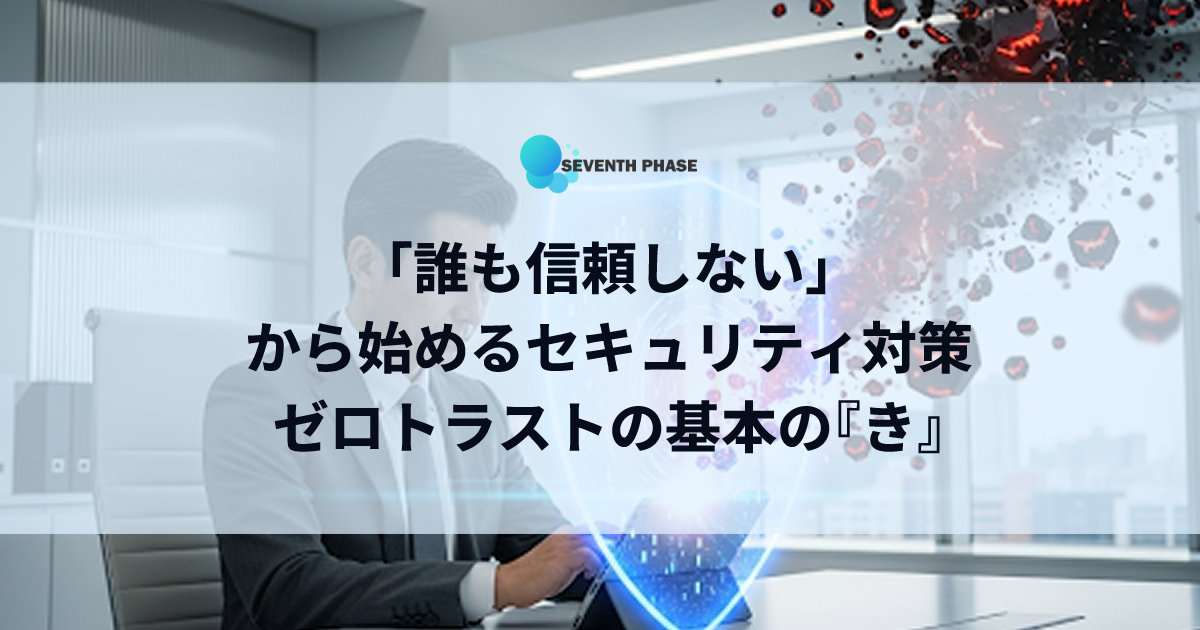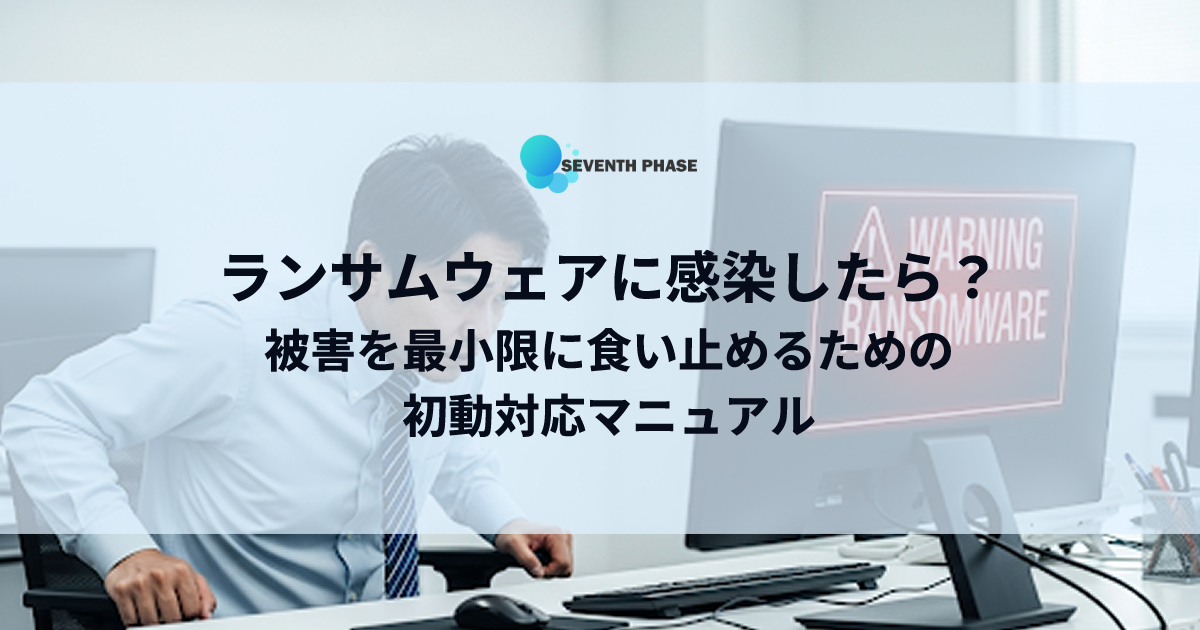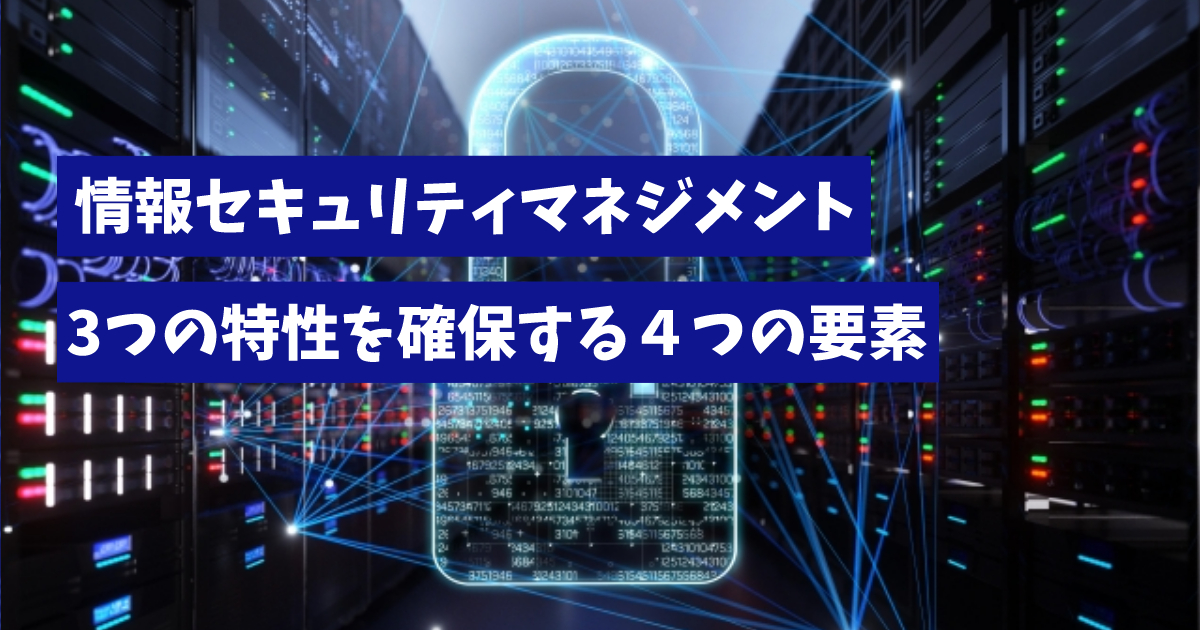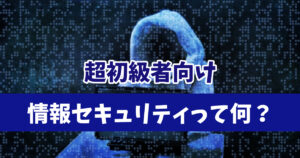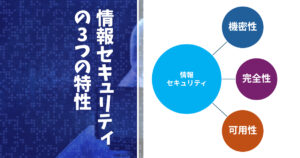昨今のデジタル社会において、企業を取り巻くサイバーセキュリティの脅威は日増しに高度化し、複雑さを増しています。従来の「社内は安全、社外は危険」という境界型セキュリティモデルでは、もはや企業の資産を守り切ることは困難です。内部不正、サプライチェーン攻撃、クラウドサービスの利用拡大、リモートワークの普及などなど、これらの新たな要素が、従来のセキュリティの「常識」を打ち破っています。
そこで今、最も注目されているセキュリティコンセプトが「ゼロトラスト」です。本記事では、「誰も信頼しない」という過激な(しかし極めて現実的な)思想から始まるゼロトラストの基本を紐解き、皆さんがすぐにでも実践できる第一歩をご紹介します。
なぜ「誰も信頼しない」必要があるのか?
かつてのセキュリティ対策は、強固な「城壁」を築き、その内部を安全な領域と見なす「境界型防御」が主流でした。ファイアウォールやIDS/IPS(ネットワークやシステムへの不正アクセスを検知・防御するセキュリティシステム)などを導入し、外部からの不正アクセスを防ぐことに注力してきました。しかし、このモデルには限界があります。
従来のセキュリティモデルの限界
内部からの脅威
城壁を一度突破されると、内部では自由に動き回れてしまいます。内部犯行や、フィッシング詐欺で認証情報を奪われた場合、その先の防御が手薄になります。
サプライチェーン攻撃
信頼しているはずの取引先やソフトウェアベンダー経由でマルウェアが侵入するケースが増加しています。
クラウドサービスの普及
企業のデータやシステムが社内だけでなく、クラウド上にも分散するようになり、明確な「境界」が曖昧になっています。
リモートワークの常態化
従業員が社外から様々なデバイスで社内ネットワークにアクセスするようになり、従来の「社内」という概念が希薄になりました。
これらの課題に対し、「すべてを疑う」ゼロトラストの考え方が、現代のセキュリティ対策の新たな指針となるのです。
ゼロトラストとは?「Never Trust, Always Verify」の精神
ゼロトラストは、米国の調査会社Forrester Researchが提唱したセキュリティモデルで、「Never Trust, Always Verify」(決して信頼せず、常に検証せよ)という原則に基づいています。これは、「たとえ組織内部の通信であっても、一切の通信やアクセスを無条件に信頼せず、都度正当性を検証する」というアプローチです。
ゼロトラストの基本原則
1. あらゆるアクセスを検証する
ユーザー、デバイス、アプリケーションなど、すべてのアクセス要求について、それがどこから来ているか、誰がアクセスしようとしているか、どのようなコンテキストか(時間帯、場所、デバイスの状態など)を常に確認します。
2. 最小特権の原則
ユーザーには業務に必要な最小限の権限のみを与え、不要なアクセス権限は付与しません。必要に応じてその権限は都度見直されます。
3. マイクロセグメンテーション
ネットワークを細かく分割し、アクセス可能な範囲を限定します。これにより、万が一不正侵入があっても、被害が広がるのを防ぎます。
4. 多要素認証(MFA)の必須化
パスワードだけでなく、生体認証やワンタイムパスワードなど、複数の認証要素を組み合わせることで、認証の安全性を高めます。
5. すべての通信を暗号化
内部・外部を問わず、すべての通信を暗号化し、盗聴や改ざんから情報を守ります。
6. 継続的な監視とログ分析
不審なアクティビティをリアルタイムで検知し、即座に対応できるよう、継続的に監視を行い、ログを詳細に分析します。
これらの原則に基づき、「すべてを信用せず、常にリスクを評価する」ことで、未知の脅威や内部からの攻撃にも対応できる強固なセキュリティ環境を構築します。
ゼロトラストを「今すぐ」始めるためのステップ
「ゼロトラスト」と聞くと、大規模なシステム改修や多額の投資が必要に感じるかもしれません。しかし、ご安心ください。ゼロトラストは一度にすべてを導入するものではなく、既存の環境に適用できるものから段階的に始めることが可能です。
小さな一歩から始めるゼロトラスト
1. 現状把握とリスク評価
現在、誰が、どのデバイスから、どのデータ・システムにアクセスしているかを把握しましょう。「最も守るべきものは何か?」を明確にし、そこに潜むリスクを洗い出します。
2. 多要素認証(MFA)の導入
これはゼロトラストの最も基本的かつ効果的なステップです。クラウドサービス、社内システム、VPN接続など、アクセスポイントごとにMFAの導入を検討してください。パスワード破りによる不正アクセスを劇的に減少させることができます。
特にMicrosoft 365やGoogle Workspaceなど、ビジネスで利用頻度の高いSaaSから優先的に導入するのがおすすめです。
3. アクセス権限の見直しと最小特権化:
部署異動や退職者が出た際に、アクセス権限が適切に削除・変更されているか確認しましょう。「この業務に、本当にこの権限が必要か?」という視点で、定期的にアクセス権限を見直し、過剰な権限を剥奪します。
ファイルサーバーや共有フォルダのアクセス権限の見直しから始めるのも良いでしょう。
4. デバイスの健全性評価
アクセスしてくるPCやスマートフォンのOSが最新の状態か、セキュリティソフトが有効か等、デバイスのセキュリティ状態をチェックする仕組みを導入します。
MDM (Mobile Device Management) や EDR (Endpoint Detection and Response) の導入を検討しましょう。
5. ログ監視の強化
ユーザーのログイン履歴、ファイルへのアクセス履歴、システムエラーログなど、あらゆるログを収集し、継続的に監視・分析する体制を整えます。不審な行動パターンを早期に発見できるよう、アラート設定を検討してください。
SIEM (Security Information and Event Management) ツールは、ログの一元管理と分析に役立ちます。
ゼロトラスト導入のメリット
ゼロトラストは単なるセキュリティ強化だけでなく、企業全体のレジリエンス(回復力)を高め、ビジネスを加速させる力となります。
セキュリティレベルの劇的な向上
常に検証することで、内部・外部からの脅威に対し、より強固な防御を実現します。
インシデント発生時の被害抑制
マイクロセグメンテーションにより、万が一侵入を許しても、被害の範囲を限定し、拡散を防ぎます。
リモートワーク・クラウド環境への対応力強化
場所やデバイスに依存しない安全なアクセス環境を提供し、柔軟な働き方をサポートします。
コンプライアンス強化
継続的な監視とアクセス制御の徹底により、各種規制(GDPR、PCI DSSなど)への対応が容易になります。
運用コストの最適化
長期的に見て、インシデント対応コストの削減や、レガシーシステムの維持コストの見直しにも繋がります。
まとめ:ゼロトラストは「意識改革」から
ゼロトラストは、特定の製品やソリューションを導入すれば終わり、というものではありません。それは、組織全体のセキュリティに対する「意識」と「文化」の変革を伴う、継続的なプロセスです。
「誰も信頼しない」という思想は、一見ネガティブに聞こえるかもしれませんが、これは「疑い続けることで、より確実な信頼を築く」という、極めてポジティブなアプローチです。あなたの会社の情報資産を守り、現代の脅威からビジネスを守るため、今日からゼロトラストの考え方を導入し、小さな一歩を踏み出してみることをお勧めします。